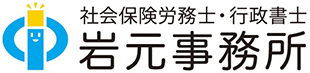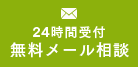注意するとパワハラだなどと言って、上司の指導を聞こうとしない部下への対応
ブログ
労働者の権利意識の高まりから、パワハラという言葉をよく聞くようになりました。しかし当然ながら部下への指導の全てがパワハラになるわけではありませんし、パワハラと言われることに過敏になるあまり、上司が部下に対して何も指導できなくなってしまうことも組織運営上の問題があります。
厚生労働省においてパワハラは次のように定義されています。
1 同じ職場で働くものに対して
2 職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に
3 業務の適正な範囲を超えて
4 精神的・身体的苦痛を与える
5 または職場環境を悪化させる行為
ポイントとなるのは3「業務の適正な範囲を超えて」という箇所でしょう。
業務上必要な範囲とは、例えば「放置すると重大なクレームを招く行動」「社会通念上当然に守るべき規律を守らない言動」「同様の職務にあたっている他の従業員と比べて著しく仕事の手段及び方法が適切でなく、能率が低い業務遂行」という事実に対してであれば、適正な範囲内と主張できるのではないでしょうか。
ただし、それがあまりに長くの時間にわたる執拗な叱責であったり、暴力を伴うものであったりした場合、4「精神的・身体的苦痛」に該当するとみなされる可能性はあります。
上司としては、できるだけ客観的事実に基づいて冷静に部下の芳しくない行動を指摘し、改善を促すようにしたいものです。